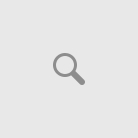気仙沼市議会12月定例会の報告第2弾は、一般質問の続きです。公共交通と交通弱者対策について整理しながら、打開策を議論しました。
■高齢者のみの世帯が1/3
急激な少子高齢化に対して、気仙沼市は好調なふるさと納税寄付金を活用した少子化対策に力を入れています。しかし、令和7年にはすべての団塊世代が75歳以上の後期高齢者入りするため、その対応が求められています。
 まずは気仙沼市の状況を整理します。高齢化率は40%を超えるとともに、高齢者だけの世帯が36%を占めています。高齢化率は65歳以上の割合ですが、団塊世代の加齢とともに75歳以上の割合が増えています。つまり、これから車の運転や外出が困難な高齢者世帯が増えていくということです。
まずは気仙沼市の状況を整理します。高齢化率は40%を超えるとともに、高齢者だけの世帯が36%を占めています。高齢化率は65歳以上の割合ですが、団塊世代の加齢とともに75歳以上の割合が増えています。つまり、これから車の運転や外出が困難な高齢者世帯が増えていくということです。
ちなみに気仙沼市内の運転免許保有者数(宮城県警察まとめ)は3万9739人で、75歳以上は13%を占めています。令和5年に免許を返納した人は268人でした。70歳を超えると返納者が増え始め、80歳前半で一気に増えています。
■利便性か効率性か。難しい両立
人口減少と少子高齢化などを受けて、気仙沼市は第2次総合交通計画を令和4年8月に策定しました。路線バスを中心とした現在の公共交通体系を見直し、BRTを軸に路線バスやデマンド交通(乗り合いタクシー等)を組み合わせた体系を目指しています。乗客の少ないバスを減らし、より便利で効率的な仕組みを導入することで、予算を節約して利便性も高めることが目的です。
しかし、現実は厳しく、どの組み合わせがいいのかという答えは見つかっていません。こうした状況で、市政懇談会では多くの地区で公共交通と高齢者の買い物対策がテーマとなりましたが、効率優先の行政と、利便性の向上を期待する市民の間が温度差を感じました。
なお、第9期高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定のための調査では、高齢者が外出を控えている理由のトップは「足腰などの痛み」であり、ドアtoドア(自宅玄関からお店等の入り口)の交通手段が必要であることが分かっています。東京都健康地陽樹医療センター研究所が気仙沼で行った大規模調査でも、1㎞以上の連続歩行について「少し困難」「全然できない」と回答した高齢者の割合は男性27%、女性40%に達しています。(調査概要はこちら)
■広い視点での政策検討を
一般質問では、こうした現状について整理するとともに、今後の展望、路線バスの運行継続基準、仙台に次いで市民1人当たりのタクシー数が多いとされる気仙沼に適していると思うタクシー補助の可能性について議論しました。結論を求めることを目的とせず、市側の認識から課題を洗い出すことを目指しました。そこで整理できたのは、公共交通は福祉やコミュニティを含めた広い視野が必要で、人口減少対策のように専門職を配置すべきということだったと思います。
 今後は、タクシー補助を導入した栗原市の状況を注視するとともに、買い物対策や福祉施策、地域コミュニティの活用について総合的に整理すしていきます。令和9年度に予定している市役所移転も、公共交通網再編の大きなタイミングになります。今後、地域での実践も加えて答えを探していきたいと思っています。
今後は、タクシー補助を導入した栗原市の状況を注視するとともに、買い物対策や福祉施策、地域コミュニティの活用について総合的に整理すしていきます。令和9年度に予定している市役所移転も、公共交通網再編の大きなタイミングになります。今後、地域での実践も加えて答えを探していきたいと思っています。
※一般質問の翌日、新聞報道を見たという本吉町の高齢女性から電話があり、タクシー補助に期待するご意見をいただきました。基礎年金を頼りにした郊外部での1人暮らしで、「買い物、通院と生きているのが大変。1か月に1回だけでもいいからタクシー代を補助してほしい」と訴えが心に響きました。ふるさと納税寄付金の活用を含めて、高齢者に優しい政策を目指します。
一般質問の詳細は次の通りです。
2. 公共交通と交通弱者対策について
人口に関する課題は少子化だけではなく、高齢化社会についても新たな発想と取り組みが必要になっています。特に公共交通については、総合的な視点による政策立案が求められています。そこで、新たな議論の展開を期待して、次の4点について質問します。
質問① 市政懇談会では、半分以上の地区で「公共交通」「交通弱者」が地域課題として挙げられました。地域は高齢者が安心して運転免許を返納し、通院や買い物、コミュニティ活動において不便がないような政策を期待しているのに対し、市からの回答は路線バス再編やデマンド交通に関して経費節減の視点が強く、その温度差を感じました。地域の交通問題について、公共交通の観点だけでなく、福祉やコミュニティなど多様な観点から政策を立案することが必要だと思いますが、地域公共交通会議は手続きの場となっており、新たな協議の場と統括的な役割が必要です。市政懇談会の感想を含めて、市の考えを伺います
菅原市長 市政懇談会での意識の差は、市民の皆さんはどれほど乗っていないかよく分かっていないからです。ほとんど空バスにお金を払っている実態です。担当課はそれが非常に悩ましいのに対して、市民の皆さんは自分が乗りたいときに乗れるものがなかったり、そろそろ免許返納しようかと思っているときに踏み切れないという現実的な感覚でお話しされたということがギャップの原因だと思っていますが、お金のことはお金で解決するしかないので、担当課も一生懸命やっています。 地域の交通課題に対する市の考えについてでありますが、本市の路線バス等の現状は、年間利用者が約18万4千人で、往復利用と仮定すると、1日あたりの実利用者数は250人程度で、本市の人口から見ると約0.4パーセントの人が路線バスを利用しているに過ぎないということが実態です。一方で、今後の更なる高齢化を考えた場合、何らかの形で公共交通を維持していかなければならないことも事実であります。この課題を解決するためには、あくまで市が中心となって、事業者や住民の事情も聞きながら素案を作成していかなければならないと思っており、地域公共交通会議はその内容をオーソライズする場であります。
利用頻度に関わらない市民が求める利便性の確保と市の負担の抑制の両立は困難な課題であります。その中で、ベストの解を求めるには、デマンド交通や住民主体による運行、事業者の形態など幅広く検討し、かつ、市内一律にこだわらないスキームを実践しながら、形作っていく必要があり、いずれの場合でも、住民のご理解とご協力をお願いすることになります。
質問② 路線バスの再編や車両のサイズダウンは、毎年10月の契約更新に向けて協議されているとのことですが、最新の契約の見直し内容、次の契約へ向けた見通しを伺います。また、同じく10月に契約更新している市内循環バスについて、ルートの延伸を求められた市政懇談会ではルートや運賃、所要時間、運行経費など、メリットやデメリットを精査して、引き続き検討していく方針が示されましたが、その検討組織、スケジュールを伺います。
菅原市長 バス路線の再編や車両のサイズダウンについてでありますが、経費削減に向け、利用が少ない路線の車両の小型化を検討しており、運行事業者とも協議を重ねておりますが、車両の確保も含め、一時に対応することは難しい状況にあります。新車(の注文)を出すと1年以上来ないという現実にぶつかるそうです。また、ミヤコーバスへの委託路線は、複数の路線を組み合わせて効率的に運行されていることから、運行事業者を替えての小型化が、必ずしも経費削減につながるとも限らず、ミヤコーさんは同じバスを1日1回使っているわけではなく、こっちにも使ったり、こっちにも使ったりしているので、そう簡単にここだけ小さくするということがなかなかできないということも言われています。結果的に複数年のスパンで運行形態や運行事業者の変更を考えていかなければなりません。
今年度は、市民バス新月線の車両小型化を計画したところでありますが、4月の乗降調査において、中学生の下校時間帯に乗客が乗り切れない可能性があったことから、実施を見送ったところであります。乗降調査は継続して実施し、現状の把握に努め、可能な路線から車両の小型化や、条件が整うところでは、デマンド交通などへの移行を進めてまいります。
市内循環バスについては、ルート延伸により、延伸地域の利便性の向上が図られる一方で、ルートによっては観光客の目的地までの乗車時間の増加や既存路線との重複区間が生じることなどが課題と考えております。実施に関しては、追加経費や他路線の再編を踏まえながら、来年度には方向性を決定してまいりたいと考えております。
質問③ 路線バスの経費は削減が進むどころか、燃油高や人手不足対策などによって膨らむばかりですが、利用者が極端に少ない路線もあり、行財政改革の視点から路線の再編を進めなければなりません。そのためには、他自治体のように収支率や利用者数などで判断する「運行継続基準」を設定することが必要だと思いますので、市の考えを伺います。
菅原市長 運行継続基準の設定についてでありますが、本市の委託路線13路線の総収入は年間約2960万円 、総費用は約2億2千3百万円であり、例えば1千円の収入に対し1万円以上の経費が掛かる路線は13路線のうち8路線あり、1便あたり2人以下しか利用がない路線も8路線あります。
休廃止を検討する上で、運行継続基準のような誰もが分かりやすい基準の設定は、一つの考え方であり、市における検討は常にそのことを意識しております。一方、実際に低利用路線を休廃止するためには、代替手段を示す努力が必要であり、この手段の検討においては一律の基準の適用だけでは必ずしも解を見つけられるものではなく、組み合わせというものが出てくる可能性もあり、結果的には総合的に可能なものを編み出していく作業をすることになります。
質問④ 市政懇談会でも話題となった乗合いを基本とするデマンド交通の課題と、地域での助け合いによる自家用車有償旅客運送の可能性について、市の考え方を伺います。なお、本市の状況からすると、安心して運転免許を返納できるように、まずは交通弱者に対するタクシー補助について可能性を模索すべきだと思いますが、市政懇談会では「財政負担も大きく困難な状況である」と答えています。タクシー補助に関する検討内容と今後の可能性について伺います。
菅原市長 デマンド交通の課題と自家用有償旅客運送の可能性及びタクシー補助の検討内容等についてでありますが、デマンド交通の課題については、利用者からはタクシーに近いサービスを望む意見が多い一方で、交通事業者からは、既存の交通事業への影響を懸念する意見も強く、妥協点の見出し方が非常に難しいところであります。また、経費面から既存路線を維持したまま、追加での導入は難しく、一部廃止を含めた現行路線の再編による実施が必要となります。
自家用有償旅客運送は、交通空白地域で市町村やNPO等が運行主体となり、自家用自動車等を使用して旅客運送を行うもので、地域における取組事例のひとつとして説明したものであります。一方で、本吉地域の山田地区のように、利用者が燃料費等の実費のみを負担し、ボランティアで運行する形態は、いわゆる互助輸送に分類されるので、自家用有償旅客運送とは違う範疇になります。国への許可や届出は要しないことから、比較的自由度も高く、このような取組も地域を支える移動手段として効果があると考えております。
また、タクシー補助については、栗原市が今年度からデマンド交通に替えて、全市的にタクシー利用助成を導入しており、利便性が高く利用も良好と伺っております。一方で、市の財政負担においては、路線バスやデマンド交通の場合、運行に係る欠損額の8割が特別交付税により措置されることになりますが、タクシー補助を実施した場合は該当しないことから、実質的な自治体負担は大きく増加することになり、現実的ではありません。
今川の再質問 議場で議論するのは難しいテーマだと思いながらもチャレンジさせていただきます。市長がおっしゃる通り、利便性と経費節約を両方とも求めるのは無理です。ただ、市政懇談会で感じたのは、市民が求めているのは利便性の向上で、今はバスを使っていなくても、いずれ運転免許を返納したら何か移動手段がほしいということなのに対し、市は路線バスを廃止するための代替交通としデマンド交通の実証実験をしていて、市民の期待に応えられていないと感じました。
そこで1点目の質問ですが、路線バスとデマンド交通だけを見ていくと市長が言う最適解は出てこないと思います。そこに福祉やコミュニティの視点が入って、初めて答えが出てくると思うのですが、公共交通会議以外に、どんな検討組織があるのかを伺います。例えば介護保険サービス、通学、免許返納特典とか、いろいろなものが組み合わさっていくことが大切だと思うので、全庁的な横断組織とか、統括する人はいるのですか。
小野寺震災復興企画部長 何をテーマに検討していくか、あるいはテーマのレベルをどこに置くかということで非常に難しい話だと思います。交通はあくまで手段であり、広いテーマとすれば、暮らしをどう支えるかという形になりますが、暮らしという風に持っていくと今度は広すぎるといったところで、どこにテーマを置いて関係する庁内課等で議論するかということで、テーマ決めからかなと思っています。それが買い物なのか食事なのか、あるいはもう少し突っ込んでいくと、例えば住宅政策まで入る可能性がありますので、どのレベルでテーマを設定して関係課で話ができるか、検討してまいりたいと思います。
菅原市長 たぶん議員さんの言ったのはイメージの段階だと思いますが、それを言ったときに各課から具体的にこれだとこうできるということが出てこないというのが、現在の問題意識です。明日の答弁にありますが、唐桑で患者バスとデマンド交通が一体になりましたが、どうなったかというと、ぜんぜんデマンド交通の利用者は増えていなくて、患者バスは増えているということで、福祉とデマンド交通はそんな関係にあるのだと分かります。これも明日の答弁ですが、学校統廃合した時にスクールバスをちゃんとやらないといけないのですが、一般の人を乗せちゃダメなのとか、そこで乗せてもらえば一路線廃止できるのではないかというようなことが出てきます。そういう具体的なことが今川議員は他の分野でも実はあるのではないかという質問だと思います。
いま2つの例を言いましたが、今回これを10人の皆さんに答弁を作成する中で、いま2つ見つけたということなので、いま突然会議を開いてもすぐ出てこないというのが、これに限らず、我々が残念ながら経験した市の状況です。その意識を持ってもらっていろんな形で解決していくことが必要ですし、いろんな補助金をもらってきて、先ほど損失の8割が交付税措置されていることですが、残り何千万円かは手出ししているわけです。この何千万円を数千万円レベルから2千万円レベルにするためにはどうするのか。3000万円で済むためにはどうするのかというものをいろんな組み合わせの中で対応していくことが必要になると思います。本当に要となって交通政策課が仕切っていく必要がありますし、実際の観点も他の部にも行ってヒアリングしてくる必要があるのかなと思っています。ただ、あまりに様々なパターンをつくると管理しにくいところがありますので、まずはできることからやって、なるべく手出し部分を減らしていく、減らせるんだというところをつくっていきたいと思います。
今川 テーマを決めて、私はターゲットの方かなと思っています。まずは高齢者をしっかりフォローすることが必要です。村上課長は優秀ですので、ぜひ公共交通専門官に任命して、いろんな部署に行って話を聞いて、政策をまとめ上げるようなポジションを与えてほしいです。人口減少対策では同じようにどこから手を付けていいか分からないという中で、専門官を置くことでいろいろな風通しが良くなったと私は思います。このテーマはいろいろな部署をまたいでいると思いました。
高齢者に絞って調べてみると、例えば(震災を機につながった)東京都健康長寿医療センター研究所の気仙沼調査では、1km以上の連続歩行が困難な方の割合で出ていて、介護保険事業の調査では足腰の痛みで外出を控えている人の割合も出ていて、そうした人たちはドアtoドアのサービスが必要になります。そういうデータがいろいろあって、集めて分析することも大事です。だからこそ、総括的な立場の人が必要だと思いました。そこはまた次の議論にとっておきたいと思います。
次にバス路線の契約更新が10月ということで、答弁は今年は新月でがんばってみたけれど成果が出せず、来年度こそは成果が出そうということですね。
村上交通政策課長 新月線について3年生が多くて一般客も含めて乗り切れない状況が散見されたため、(今年度契約更新でのサイズダウンは)一度断念しました。来年度は生徒の数等を考慮しながら実施に向けて地元と協議を進めているところです。
今川 そうすると来年10月の契約更新で出てくるのは新月線のサイズダウンだけということですか。唐桑のデマンド交通に伴う路線バス再編など他の候補はまだピックアップできていない状況ですか。
村上交通政策課長 来年度の再編予定としては、唐桑地区でデマンド交通の実証運行をしており、条件が整うエリアへ横展開してきたいと考えています。候補になる路線について目星はつけていますが、地元と今後協議しながら最終的な決定をしていきたいと考えています。
今川 市の総合交通計画の期間である令和8年度までに、路線バスの市負担を1.7億円(令和2年度)から1.3億円まで指標がありますが、減らすどころか2億円まで膨らみました。節減の難しさを痛感していると思いますが、廃止する路線を決めてデマンドや代替交通を考えることが必要だと思います。面瀬のようにバス路線は廃止できないし、デマンド交通も失敗したとなると、どういう地域交通を目指したいのかということなります。市としてしっかりとした考えを持って進めるべきではありませんか。。
村上交通政策課長 市長答弁でもお話ししましたが、1便当たり2人にも満たない路線が多数あります。そうした中で、そういった路線をどうするべきかしっかり検討しなければならないと考えています。例えば、そのような路線が近くに2つあった場合、路線バスでは線でしかつなげられませんが、デマンド交通なら面的に停留所が置けるというメリットもありますので、その2路線をデマンド交通の1路線1エリアとして再編するなどの検討は今後していきたいと考えていきます。
今川 その時には路線バスの委託費よりデマンド交通が安くなるということが大前提だと思いますので、そういった研究をしてほしいのと、利用者が代替交通の一番の対象となりますので、利用目的に対して代替手段となるのかがポイントになります。利用者の実態調査は進んでいますか。
村上交通政策課長 実態調査は昨年度に全路線へ職員が乗車してどのような方が利用しているのか状況を把握しました。今年度は4月と10月に1カ月間、停留所の乗降データを交通事業者から頂いて本課で集計してデータ化を進めています。
今川 市政懇談会では自家用車両有償旅客運送という制度が何度も示されたので、市として進めていくのかなと思ったのですが、本吉町山田地区の事例とは異なる制度でハードルが高いと思いました。市政懇談会の感想も含めて考えを伺います。
村上交通政策課長 市政懇談会では多くの地区で公共交通または高齢者の買い物に関する課題が挙げられました。高齢化が進む中、自分で車を運転できなくなった場合の不安を抱いている高齢者が大変多くなっていると感じました。自家用車有償輸送は議員さんの言う通り、なるべく分かりやすく地域の方へ説明しようと使わせていただいた言葉ですが、その制度は必ずしも本市が目指した山田地区のような互助輸送と違うところが出てきます。その部分についてはこれから丁寧に説明していたいと考えています。
菅原市長 自家用車有償旅客運送については私が勉強不足で山田地区のようなところは互助輸送というんだということがよく分からなくて、回答を直したのであのミスリードしたなと実は思っています。感想ですが、反応はあまりなかったというのが残念ながら素直な感想です。それで急がば回れなのか、回り切れないのか分からないのですが、山田地区のことも含めて見ると、要は地域コミュニティがしっかりとして初めて成り立つとうことで、例えばですけれど、自治会で草刈りでも何でも一緒に参加率も高くて、バーベキューもやってますとか、太鼓もやっていますとか、若い人も参加する行事が維持されていくことが、実は交通対策としては急がば回れという意味だと思っています。
例えば災害公営住宅でみんなで何かやりましょうといってもほぼできないですし、運動会も開かれない地域でその話をしてもどうするのとか、現実的にはあると思うので、実際、今のコミュニティ活動というものを大切にしなくちゃいけないし、そういうことを促していくことによって、相当部分が救われてくると思います。というのは、毎日乗らないんです。同じ人が毎日乗ってくれればやりやすくて、タクシー補助も難しいけれど数が見えます。数が見えないところにはできないですし(予算も)膨大になります。
タクシー補助は、1日250人に往復1000円ずつ補助したとして、300人だと1億5000万円です。交付税措置はゼロ。乗る人は完璧に把握されたとしてもそういう状態になってしまうので無理なんです。そういう意味で地域のことを大切にしていくことを市政懇談会の中で感じました。
今川 最初に質問した集会施設でも地域コミュニティの話がありましたが、そうした(互助輸送など助け合いの)拠点になっていくのであれば、集会施設の整備を市で応援していく意味があります。施設を整備する際にはそういう話をしてほしいです。山田方式については、南三陸町入谷と同じように小さいコミュニティで成り立っていて、大きな自治会単位では難しいだろうと思います。山田方式の次のステップとして、もう少し人数を増やしたらどんな仕組みがいいのか、まちづくり協議会が関わればいいのか、モデル的な仕組みを示さないと進みません。例えば市が車を提供するなど応援できること、地域でしなければならないことをまとめて、地域に説明できませんか。
菅原市長 その観点だけだとうまくいかないと思います。なぜ山田地域は成り立つのか。それは運転する方の担い手としての強い意識の問題もありますが、そうでなくても十分かどうかは別として、本吉の場合は役場、郵便局、信用金庫、スーパー、歯医者、病院がひとかたまりになっています。唐桑はそれができなくて(デマンドの)利用者が増えません。それを鹿折まで持ってきますかとなると、便数は半分になります。成功条件というものを分析したうえで制度としてどうするかという縦横の検討が必要だと思います。片方だけやるとほぼ失敗するのではないかということも今のところ学習したところです。そのことも含めて交通政策課の仕事だと思っています。
今川 個人的にはファミリーサポートセンターみたいな仕組みで、応援したい人と応援してほしい人の登録制度が、気仙沼だとうまくできそうだと思っています。ただ、法規制を考えると難しいなと思いますので、別な機会にお話ししたいです。最後にタクシー補助ですが、年間何億になるよう試算では続かないと思います。しかし、選挙の投票所への移動支援としてタクシーを無料化してときのように条件を絞ったり、障害者への福祉チケットのように配付枚数を決めたりすれば、半額補助とかなら無駄な利用は考えられないし、そんなに大きな予算規模にならないのではないかとは思います。そこで、運転免許返納者への(期間限定の)タクシー補助をしている自治体が多いので、本市でも試行的に行ってみて、どんな目的でどのくらい使われるかデータ収集してみませんか。
小野寺震災復興企画部長 交通に関してはトライ&エラーとして一回やってみますか、でやめますかという話はなかなか通じるものではないかと。要はそこでの利便性を享受してしまうと、それはずっと続けなければならないと、そういう覚悟をもって導入するならやる必要があると思います。それと、コミュニティと交通の関係でファミリーサポートセンターのようなマッチングの話がありましたが、いま、コミュニティと交通の関係でうまくいっているのはコミュニティカーシェアリングという考えがありまして、ベースはコミュニティです。そこでサロンを開く、健康体操するという中に、買い物ツアーもするみたいなコミュニティがベースとなってそこに交通が加わってくるということが、世の中で成功事例としてありますので、例えばサロン活動が行われている自治会よりも少し小さなコミュニティで、サロンとともに毎週金曜日に買い物ツアー行きますかみたいなことができるかどうかです。それにつけても、地区とかコミュニティとか小さなグループとかで、課題感の共有がまずもって必要になります。私たちもこういう事例がありますよということについては課題が上がってきたところには紹介してまいりたいと考えています。
菅原市長 タクシーチケットを増やしたときにデマンド交通が成り立つのか、それは利用者だけでなく交通事業者はどう考える方向に行くのかという怖さというか、当たり前の経済活動の動きがあるわけです。その時に一方的に市だけ負担が増えていく、利用者、交通事業者、市の関係で、どういう帰結になる仕掛けになってしまうのかという観点でも見ないと逆戻りはできないものであるとすれば、大変難しいことではないかと思っています。今までタクシーチケットは別なお金(財源)があって、投票、ワクチン接種もそうです。ちょうど交通事業者も利用者が少なくて困っていた時でしたので、良かったと思うのですが、みんながそれなりにいいようにということを念頭にいろんな政策は考えていかなければならないと考えています。
今川 たぶん来年の市政懇談会でもこのテーマは続いて、今年と同じような答弁はできないと思います。ぜひ1歩でも2歩でも進んだような話ができように1年間頑張ってください。事例として紹介された栗原市の推移も注視しながら、タクシー補助の可能性や交通弱者、公共交通について考えていきたいと思います。またこのテーマで質問したいと思います。ありがとうございました。