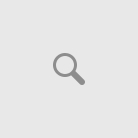遅くなりましたが、気仙沼市議会12月定例会の報告です。第1弾は一般質問の前半部分で、集会施設の官民格差について議論した内容を説明します。
■旧市町で異なる制度が発端
集会施設の官民格差は、市町合併から続く課題です。旧気仙沼市では自治会の自立心が高く、地域で自治会館を建設・運営し、市が建設費のうち300万円を補助してきました。一方、旧本吉町は町と振興会(自治組織)の連携が強く、町が振興会館を建設して振興会がその2割を負担する形式をとり、町が指定管理料を支払って振興会が管理してきました。旧唐桑町は町が集会施設を建設・運営し、管理人に鍵の開閉等を委託していました。
合併後、まずは旧本吉と旧唐桑によって異なる市の集会施設の運営方法を統一する予定だったのですが、震災によって集団移転団地や災害公営住宅に復興予算によって集会施設を整備できることになり、市所有の施設が旧気仙沼市地域でも一気に増えてしまいました。この流れで市所有の施設は地域による指定管理で統一し、旧本吉町の地元による建設費一部負担がなくなるとともに、老朽化した旧唐桑町の施設をすべて市が建て替えることになりました(旧施設の解体、移転先の用地確保を含めた新築費用は延床面積154㎡の崎浜集会所で約6800万円の実績)。
※復興に伴う集会施設の補助制度改定は平成26年6月の市議会東日本大震災調査特別委員会で説明された(資料はこちら)
■市で建てる施設、自治会の2割負担で建てる施設
旧気仙沼市で自治会が所有する施設は、建設・建替えで上限300万円の補助でしたが、建設費の8割まで引き上げることで、格差是正を図りました(下表参照)。しかし、市が建設して管理費まで支払う施設と、地元が建設費の2割を負担して市から管理費の支援がない施設の差は残されてままでしたので、機会あるごとに市の考えを問いただしてきましたが、ハッキリしない答弁が繰り返されてきました。
しかし、看過できない動きがあったので12月定例会で取り上げました。それは、11月に開かれた津谷・小泉地区の市政懇談会で、老朽化した旧本吉町の集会施設を市が建て替えていく方針とともに、現施設にエアコンも設置することが説明されたことです(懇談会資料はこちら)。市の施設だから当然のことではあるのですが、自治会がエアコンを設置する際の補助率は1/3なので、格差が拡大することを懸念したからです。
■増築・修繕の補助率を1/3 ⇒ 8/10へ引き上げ。エアコン設置も
このタイミングでの質問ですから、市はようやく格差是正の新方針を示してきました。自治会による建設への補助率8/10は堅持したものの、これまでエアコン設置も含めて増築・修繕は補助率1/3でしたが、8/10へ引き上げるための財政的な検討を進めることにしたのです。さらに、自治会にも指定管理料と同程度の維持管理費(電気・水道の基本料金と浄化槽維持費等で平均で年10万円程度)を補助することも一緒に検討されます。
格差は是正されたものの解消には至らず、そもそも市が自治組織の集会施設まで建設する必要があるのかも含めて、機会を見て議論を続けていきます。なお、集会施設の課題については平成27年10月の気仙沼復興レポート⑳「集会施設の市有化と課題」で詳しく説明しています。
公共交通問題の本質に迫る一般質問の後半部分は、後日報告します。今年の目標の一つに、「週1回以上はホームページを更新すること」を掲げていますので、定期的なチェックをお願いします。
※個人的なことですが、昨年12月17日に父(享年77歳)が他界しました。そのため、12月定例会の最後の2日間を欠席してしまいました。父の遺品を整理していて、初めて知ることもありました。息子が紹介された新聞記事も切り抜いて保存してありました。母が亡くなってから14年、晩年の父は口数が少なくなりましたが、どんなときでも応援してくれていました。その期待を絶対裏切らないように、コツコツと努力を続ていきます。
■12月定例会一般質問(前半部分)の詳細はこちらです
今川悟一般質問 2024.12.16
1. 集会施設における官民格差の解消について
市町合併後、市内にある集会施設において、自治組織所有と気仙沼市所有の施設で整備費や維持管理費についての格差が課題になっていました。震災復興によって市所有施設が増え、さらに市政懇談会で本吉地域の市所有集会施設の施設更新と会議室へのエアコン設置という新たな方針が示され、その格差はさらに広がることが心配されますので、次の4点について質問します。
質問① 市が所有する本吉地域の集会施設について、唐桑地域の施設整備後となる令和10年度以降に他の老朽化施設と合わせ、優先順位を決めたうえで順次整備する方針が、市政懇談会で示されました。旧本吉町時代の集会施設は、地元が建設費の2割を負担する形で整備されましたが、今後は地元負担を撤廃することになっています。旧本吉町に合わせて制度設計した自治組織所有施設に対する新築・改築の補助率10分の8について、その制度案が示された平成26年6月の東日本大震災調査特別委員会で、これが最終段階であるか確認した際、市当局からは「いくつかのステップの中の一つだと思う。どのような形にしていくのかはこれからの話し合いになると思う」との答弁がありました。増築・修繕等の補助率3分の1と合わせて、公平性確保の観点から見直す時期に来たと思いますが、市の考えを伺います
また、本吉地域の市所有集会施設では、暑さ対策として会議室にエアコン設置する方針が示されました。一方で、自治組織所有の集会施設のエアコン設置の補助率は3分の1となっており、公平性の観点から補助率を見直すことについて、市の考えを伺います。
菅原市長 集会施設における官民格差の解消についてでありますが、市所有の集会施設については、市が責任を持って適正な維持管理に努める必要があることから、老朽化した施設については、状況を踏まえながら整備していく予定としております。
気仙沼地域の集会施設のうち、自治組織所有の施設については、建築等に係る支援策として市町合併前の補助率3分の1の上限300万円から、8割補助に拡充したところであり現制度を今後も継続してまいります。
エアコンの設置を含む施設修繕等の補助率については、建築等に係る補助率にすることを前提に、財政負担の検証をしてまいります。なお、市所有集会施設に対するエアコンの設置については、本吉地域だけに限らず、気仙沼地域、唐桑地域にある市所有集会施設についても、使用頻度の高い部屋を対象に2年を目途に整備してまいります。
質問② 市所有の集会施設は指定管理者制度を導入して、年間10万円前後の維持管理費分を市から支出していることから、自治組織所有の集会施設に対しても同程度の支援を検討すべきだと思います。自治組織所有の集会施設における維持管理に関する課題と格差の解消について、市の考えを伺います。
菅原市長 集会施設に対する支援についてでありますが、本市が所有する集会施設については、本来、市が直接管理するものを指定管理により自治会等へ依頼しているものであり、電気、水道、ガスの基本料金と浄化槽の維持管理料を指定管理料としてお支払いし、利用に係る従量分については、主な利用者となる指定管理者において負担いただいております。
また、自治組織所有の集会施設における維持管理費については、市所有施設の指定管理料と同様の積算で維持管理料を補助する方向で検討してまいりますが、自治組織所有の集会施設はその形態も様々であることから実態を調査し、また財政負担も考え合わせ進めてまいります。
質問③ 市公共施設等総合管理計画に基づいて令和2年に策定した個別施設計画では、市の集会施設について地元自治組織への譲渡を検討するとともに、本吉地域の施設は令和8年度から11年度にかけて大規模改修で対応する計画内容となっており、29施設うち19施設で計約11億円の事業費を想定しています。新築も認めるという新たな方針に合わせて個別施設計画を見直さなければなりませんが、官民格差の是正をはじめ、持続可能な指定管理の在り方、公民館の多機能化による集会施設の再編促進策について、将来を見据えた指針も策定すべきと思いますので、市の考えを伺います。そもそも地域コミュニティと地域防災力の向上を目的としている集会施設について、市所有と自治組織所有で何が違い、なぜ格差を是正しようとしないのかについても伺います。
菅原市長 平成29年3月に策定した「気仙沼市公共施設等総合管理計画」では、中・長期的視点から財政負担の軽減・平準化を図りながら、長寿命化や集約化・複合化など適正配置に取り組むこととしております。実際の建替えや大規模改修等に当たっては、個別に検討し、市民の理解を得ながら適切な対策を講じるものとしており、その時々の状況や状態に合わせ進めるものと認識しております。本吉地域や気仙沼地域の集会施設整備については、老朽化が著しい唐桑地域の集会施設整備後に、状態の検証や地域との協議を経た上で、財政状況を踏まえながら順次進めていくことといたします。
なお、市全体の集会施設については、補助率などの見直しの検討により、市民の負担面で旧市町が近づいてきてはいるものの、それぞれ違う形で地域コミュニティを進めてきた経緯があり、旧市においては自治組織であるという良い点も踏まえて時間にこだわらない検討が必要と考えます。
今川の再質問 まず答弁を確認します。自治組織所有の集会施設整備の補助金は、新築・改築が10分の8のままで継続し、増築・修繕については10分の8に引き上げることを財政面も含めて検討するということですね。エアコンについては再度確認します。維持管理費についても、市所有施設と同程度で電気代等を交付することを財政面も含めて検討していくという答弁内容ですか。
菅原市長 エアコンは自治組織所有の施設修繕等の補助率について建築等にかかる補助率にすることを前提に財政負担の検証をすると答えています。エアコンを設置するとなれば、8割ということになりますが、どの部屋もということではなく、一番使う部屋については考える対象にしたいということです。市所有施設は本吉を含めて使用頻度の高い部屋を対象に、2年以内ということですが、1年は物理的に簡単にはいかない可能性があるので、2年かかるのではないかと話しているところです。
あと、自治組織所有施設の維持管理については、市所有で指定管理をお願いしている施設と同じで積算して、その分は補助としてお渡しするということで考えているということです。ともとのお話しで、私の答弁と違っているのは、自治組織をどう考えるかということです。実際、考え方がさまざまあると思います。どっちが尊いとは言いかねないのだと思います。そういう意思がより以前にはあったと思います。自主組織でちゃんと気仙沼はやっているのに旧町では町で建てることだったの、本吉はがんばって民間が2割出していたというイメージでした。それを今川議員の質問は市が全部出せばいいということを貫かれていますが、そう一概に言えますか、ということをお話ししました。それで、8割にした理由は明確で、震災特別委員会でも何回も話していると思うのですが、大震災の後に地域避難所を回ったときに、やはり旧気仙沼が弱かったと、直接的に被害に遭う平らな海岸近くにあったところが多いということもあるのですが、それ対して本吉と唐桑は古い新しいに関わらず、そこに皆さんがきちんと避難して、誰がいなくて誰が亡くなってしまったのか数字もあっという間に把握できたのに、気仙沼は1カ月たっても2カ月たっても分からない部分がありました。そういう意味で集会施設については自治組織であっても早急な整備というか支援が必要だということで8割まで上げました。なぜ9割とか7割とかではないということについては、そこは本吉の事例に関わってそうしたという、それに対してどれほど深い意味があったかというと、取り方だというのが今の状態だと思います。
今川 基本的に今まで3分の1補助だった部分を10分の8に引き上げるように制度設計を見直すということで理解しました。市長がおっしゃる通り、この質問をするにあたって悩んだのは、集会施設をどんどん建替えていくことを促したいからではないからです。世の中の流れからすると、(利用者が限定されている)集会施設は地域へ譲渡する方向で進んでいます。保育施設や学校へ限られた財源を向けるべきとも思いましたが、まずは格差の是正について議論していかなければと思いました。再編とか集約は次の議論だと思っています。そういう意味では、2割負担があった方が必要なところだけ建設して、10割補助というのは本当はやってはいけない部分だと思いますので、今の答弁で納得しました。確認したいのは、この話を自治組織の代表者たちとしっかり議論してほしいと思うので、どういうタイミングで話し合い、どんなスケジュールで進めていくのですか。
菅原市長 ちょっと確認すべき点があると感じました。気仙沼地域の市所有施設において地域への譲渡みたいなことを以前の(個別施設)計画に書かれていることですが、まあ無理ですよね。受ける方に理由がないということで、どういう流れで書かれたかは分かりませんが、私は実際的に期待することではないと思っています。
もう一つ、実際に市が8割補助になってからもちゃんと2割貯めて自分たちで計画してくれたところがいくつかあるし、今も貯めつつあるところがあるというのは、一つ大きな私たちとしては頭に入れておかなくちゃならない。公平性ということだけではないのかなと考えました。そういうところを確認したうえで、先ほどお話ししたようなこと、財源の方をさらに確保したうえで、自治会の皆さんにお話しして、こういう方針ですということを、これはエアコンの問題もあるので、なるべく早く機会があれば担当の方から話していくことが必要だと思います。あと一点、建てていくこともそうなんですが、市の施設が今後、人口減少の中で古いものばっかりかもしれませんが、学校が公民館に一部変わっていったと同じような意味合いで、市の施設の有効利用というものが地域の施設の確保と合わせて常に考えていく必要があると思いました。
小野寺震災復興企画部長 (制度改正の)時期についてですが、財政負担の検証をしっかりしてからじゃないと制度設計もできませんので、まずもっとそちらの検証を進めて、制度設計できましたら、遅滞なく自治組織等には説明したいと思います。
今川 補助率の引き上げが来年か再来年かということですが、トイレの水洗化だと現在は3分の1補助が10分の8になるわけですから、工事を待とうということになると思いますので、早めに進めてください。管理費の補助についても同じです。今回の答弁によって、ステップはまた一つ上がりましたが、市の施設の民間施設の格差は残っています。こうした格差を未来永劫残し続けることは避けたいので、最後には一緒になるというビジョンが必要だと思いませんか。
小野寺震災復興企画部長 まずもって市所有か自治組織所有かという大きな違いがあります。そこは前提として、それでも合わせるかどうかとなると、そこは全く条件が違うと思います。それと自治組織についても旧市町で違った形でコミュニティがつくられているので、いつまでにどうのということではなく、長い時間をかけながらということかと思っています。
今川 ここがゴールではないと確認できればいいです。先ほど市長もおっしゃったとおり、ハコモノをどんどん作り続けることは私も疑問に思っています。特に公民館とか学校跡地とかいろいろな建物がある中で、あえて近くに集会所をつくるということなれば、そこは誘導してほしいです。これは唐桑の時にも念を押したのですが、実際は地域に話を持っていくと、自分たちの施設がほしいということになってしまいました。市として何かしら基準とか指針とか持っていないと、地域との話し合いはうまくいかないと思います。今後、市所有施設の建て替えについて優先順位の話し合いが始まりますので、手遅れにならないように備えてください。建て替えの際にこうした話はできますか。
菅原市長 すぐにはできないだろうというような答弁を私からも小野寺部長からもしました。ルールとか基準とかというのは8割、9割が当てはまればできますが、半分しか当てはまらないようなものをつくっても、すぐに違うものが出てきます。この問題については8割、9割同じようにできるかというと、特に歴史的背景だとか、自治組織というのはそれの価値はちゃんとあると思っているので、いま行政の方で自治組織を無視して市が作るものをビジョンと言えるかというと必ずしもそうではないと思います。それよりは活用がしっかりしていて、その結果としてどういうものが必要か、行政の関りがより必要なのか、そうでもないような社会が生まれてくるのか、そういうようなことも含めて見ていくことになると思っています。
今川 これからハコモノをどうやって減らしていくのか、公共施設等総合管理計画の改訂もあると思いますので、そういった議論の中で追求させてもらいます。