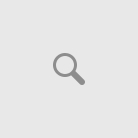気仙沼市内にあるリアス・アーク美術館は、気仙沼市と南三陸町で構成する気仙沼・本吉地域広域行政事務組合で運営してきましたが、令和8年度から気仙沼市に移管する準備を進めています。その経過をまとめました。
・組合議会に示された移管に向けた方針はこちら⇒美術館の市立化方針2024.7
・組合議会で説明された移管に向けた検討状況の資料はこちら⇒美術館移管のの検討状況2025.3.25
令和7年3月24日
今川悟 作成資料
リアス・アーク美術館の在り方へ向けた基礎資料
■施設概要 宮城県が建設して気仙沼・本吉広域行政事務組合が運営。平成6年に開館し、同16年に県から組合へ施設が譲渡された。組合の構成市町は1市5町(気仙沼市、本吉町、唐桑町、志津川町、歌津町、津山町)でスタートしたが、市町合併によって現在は気仙沼市と南三陸町となった。3階建て、総面積4601.22㎡
■設置目的 地域における文化創造の拠点施設として、圏域の住民に質の高い芸術文化に触れる機会の提供と、住民の創作活動や発表の場の提供を通じ、美術的な視点から個性豊かな圏域文化を創造しようとするもの(震災後、津波等災害の後世への伝承を加えた)
■位置づけ 地域文化創造プロジェクト事業の中核施設として、東北・北海道を一つのエリアと捉え、継続的に調査・研究することを基本方針に、常設・企画事業を展開している。県の広域活性化プロジェクトでは、登米祝祭劇場(登米市)、仙南芸術文化センター(大河原町)、大崎生涯学習センター(大崎市)、くりはら交流プラザ(栗原市)も整備された
■観覧料 常設展は一般700円 高校生500円、小中学生350円(令和3年度から150~200円値上げ)。地元の小~高校生には無料パスポート発行
■スタッフ 12人(うち会計年度任用職員7人)
■公共施設等総合管理計画 (令和5年3月策定)
・美術館は法定耐用年数50年に対し、長寿命化によって80年の使用を目標にした
・令和5~14年度までの10年間で4.45億円の改修を計画
・令和9年度に大規模改修で空調更新(2.3億円)、翌年にはエレベーター(8800万円)の予定
※概況 美術館施設が先行したため、目玉の展示物がない状態で開館。十分な予算を手当てできないことから、東北・北海道の若手作家を発掘して紹介する形で作品を寄贈してもらい、展示物を確保してきた。歴史・民族系を含めて、30年間の蓄積によって展示物を確保してきた。
■ふるさと市町村計画と基金の経緯
| 平成4年 | 気仙沼・本吉圏域(当時は1市5町)がふるさと市町村計画の地域に選定 | |
| 平成5年 | 基金造成 | 宮城県からの補助金1億円に、1市5町の出資金を加えた6億円を原資にした基金で、その運用益(金利約5%で年3000万円と想定)を美術館運営に充てる計画だった
※平成13年の運用益は最高の2275万円。平成14年は29万円だった |
| 平成6年
|
美術館開館 | 総事業費28億1660万円。均衡ある県土発展のため、広域圏活性化プロジェクトとして宮城県が建設。組合に10年間無償貸与。その間、組合が管理運営する |
| 平成16年
|
県から組合へ施設を引き渡し | 施設補修費も組合の負担となった。運用益では計画遂行の財源が賄えない情勢となり、市町の議決を得れば出資金を取り崩して財源にしていいことにした |
| 平成17年 | 津山町が登米市へ合併するため出資金980万円を返還 | |
| 平成18年 | 基金の取り崩しを開始
※県を除く出資比率は気仙沼市90.596%、南三陸町9.404%。この割合で計画の経費を負担する |
|
| 平成20年 | 総務省がふるさと市町村圏推進要綱を廃止 | 気仙沼・本吉圏域では自主的協議の結果、基金存続とともにこれまでの基本的制度を継続することで合意 |
| 平成31年
|
博物館法の博物館として登録 | 県内外の博物館と展示物の相互貸借がしやすくなる |
※市長は気仙沼市の人口6.7万人で1.2億円を負担していたころ、年間1人1800円なので映画を1回観るのと同じと説明していたが、5.6万人で1.45億円(基金取り崩し分除く)だと約2600円になる
【ふるさと市町村圏計画広域活動計画】(令和3年3月策定)
■計画期間 令和3~7年度の5カ年計画 ⇒ふるさと市町村圏計画2021-2025
■活動費は年間966万~2078万円(基金取崩制度の導入時から自主企画・特別展企画事業は気仙沼市の単独負担としたことで、南三陸町の負担は共通経費を出資率で按分した48万から90万円。電気料は気仙沼市の教育費負担金へ移行した)
| 自主企画事業 | 東北・北海道在住の若手作家を紹介する「N.E.blood21シリーズ」は毎年300万円の予算 | 気仙沼市単独負担分 |
| 特別展・巡回展等開催事業 | 5年に1回、遠方の美術館等でなければ見られない作品の鑑賞機会を提供する。次は令和6年度に開館30周年記念展(9/18-10/27)として開催。地元高校生と一緒に考えた「デザインってなんだ?」をテーマに、グラフィックデザインなどを展示した | |
| 常設展示 | 誇りある三陸文化の顕彰と振興として、食文化を中心とした歴史・民族系の展示をしている。美術品は「N.E.blood21シリーズ」の作家から寄贈された作品を蓄積する形で展示している | |
| 地域文化のデジタルアーカイブ | 生活文化や震災の映像や写真をデジタル化し、ハイビジョンギャラリーで上映する | |
| 教育復旧事業 | ワークショップや子ども向け工作教室、オープンアトリエとして利用。学芸員による出前授業も | |
| 文化祭事業 | 平成15年から方舟祭りを主催 | |
| 公募展開催事業 | 東北・北海道の特色を生かした「LANDSCAPE of N.E.東北北海道の風景と私」展(2年サイクルで計183万円の予算)、リアス・ジュニア絵画コンクール展 | |
| 歴史・民族・生活文化の企画展 | 継続事業として「食と地域の暮らし」展を開催。「LANDSCAPE of N.E.東北北海道の風景と私」展と交互に隔年開催してきた | |
■計画策定住民協議会- 計画策定に広く住民の意思を反映させ、計画推進に対する住民意識の高揚を図るために設置。文化協会長など8人以内で構成
■基金データ (万円)
| 出資額 | 平成18年 | 平成22年 | 平成27年 | 令和2年 | 残 高 | |
| 気仙沼市 | 44410 | △18070 | △11587 | △9189 | △3962 | 1600 |
| 南三陸町 | 4610 | △1045 | △221 | △103 | △239 | 2999 |
| 宮城県 | 10000 | 10000 | ||||
※津山町は登米市の合併に伴い980万円を返還
※前計画の残高2288万円
※基金を廃止する際は県補助金の返納を条件に知事承認が必要
■現計画(令和3~7年度まで)策定の経緯
| 平成30年11月27日 | 今川悟議員の一般質問に管理者は 「抜本的な見直し必要」と答弁 |
| 平成31年3月(更新2年前)
※次期計画だと令和6年3月 |
住民協議会で次期計画策定スケジュール案示す
案では31年度中に計画概要、基金運用方針を検討 |
| 令和元年11月29日 | 今川悟議員の一般質問に管理者は 「基金枯渇しないで次期計画」と答弁 |
| 令和2年3月(更新1年前)
※次期計画だと令和7年3月 |
住民協議会計画案を示した
→電気代1640万円を気仙沼市の負担に戻したことで基金枯渇は回避 |
| 令和2年7月1日 | 住民協議会で確認 |
| 令和2年7月31日 | 組合議会全員協議会へ計画案説明 |
| 令和2年9月1日 | 組合議会全員協議会に見直し案
・人件費や電気料を削減 ・観覧料を値上げ ・「圏域住民とともにある美術館」を目指すために円卓会議設置、30周年記念展企画ワークショップなどに取り組む内容を示す |
| 令和2年9月(次期7年9月) | 市町議会で基金取り崩しのための議案を議決 |
| 令和3年2月 | 組合議会で議決 |
■円卓会議
・令和3年度に教育普及事業として円卓会議を設置。メンバーは地元のクリエーターや市職員ら若者11人
・令和6年2月に「リア美もったいないプロジェクト」で考えたアイデアをメンバー5人が発表した
・ゆるキャラのホヤぽーやとオクトパス君、ハイビジョンギャラリーの活用などを提案
■令和7年度予算
・ふるさと市町村圏振興費1111万円(ふるさと市町村圏基金からの繰入金)
・美術館管理費1億5732万円は観覧料約300万円や雑収入、組合債を除いて気仙沼市負担
※計画では気仙沼市の教育費負担金は1億円程度を見込んでいたが電気代高騰と会計年度任用職員制度が影響して上回っている。観覧料も600万円台を計画していた
・支出は約7400万円が人件費、約3200万円が光熱水費と燃料費、管理委託に約3200万円、施設改修に約1100万円など
■現計画終了後に向けた議会での議論 ①
| 質問概要 | 答弁概要 | |
| 令和4年
7月29日 今川悟議員の決算質疑 |
円卓会議が教育普及活動としての位置づけであれば、計画期間が終わった後の美術館の在り方はどこで議論するのか | ・令和7年度になったら美術館がまるっきり違うものになるという話ではないということが当局の基本的考え
・例えば8割が10割になっていく可能性があり、より一層住民の理解を得たい ・大切な美術館という認識があって初めて予算が出る。そこを担保するのが令和7年度までの課題。発信とか市民要望の受け皿を積み重ねて市民にとって大切さを増す美術館の運営を示すということだと思う |
| 令和5年
11月30日 今川悟議員の一般質問 |
広域活動計画及び基金の在り方について、2年前の答弁では「関係機関と十分な協議の下で今後進めていきたい」との方針を示したが、現在の検討状況、今後のスケジュール、そして管理者としての基本的な考えは | ・基金残高予想に鑑み、これまでより1年早めて令和6年度から計画と基金の在り方について議論する
・次期計画の根本的な在り方などを含む美術館の管理運営計画を作成する予定である ・広域計画をこれまでの形でやることがいいのか、気仙沼市が必要分を拠出して基金という形でなくてもいいのか、または基金化の方が美術館として動きやすいのか、そのことを含めて検討することになる ・美術館の活動として計画は5年が適切なのか、10年のほうがいいのかも検討すべきことの一つだ。なるべく分かりやすい形で運営し、美術館が魅力を増す形をとることだと思う |
| 基金に宮城県が拠出している1億円について、「返さざるを得ない」と答弁してきたが、その期限等についてどのように協議・検討しているのか | ・今年8月に県から基金の活用状況にいてヒアリングがあった。全ての圏域のヒアリング結果を踏まえ、補助金制度の維持や返還時期などの取り扱いについて検討していくとのことだが、方針が示される時期は未定である | |
| 今後の選択肢として、美術館運営費(令和5年度当初予算で約1億5600万円)の実質95%以上を負担する気仙沼市に移管するという可能性はあるか | ・現在の運営状況からすれば一つの検討課題と認識している
・一方でもこれまで南三陸町民にも支えていただき親しまれてきたことにも留意する必要がある |
|
| 美術館を広域行政事務組合で運営するメリットとデメリットは | ・デメリットは広域施設であるがゆえに一般的に施設名に付される地名を入れられないという理由から、所在地を特定することが難しいこと、公立博物館として運営組織の説明が一般的に理解されにくいなどが考えられる
・メリットは博物館施設として三陸の歴史文化を広域圏として包括的に調査研究、資料収集・展示できることで、開館以来30年蓄積した資料の有効性を考慮すればそのメリットはさらに大きいといえる ・広域で美術館を運営している例は珍しい |
|
| 公共施設等総合管理計画の個別施設計画(令和5年3月策定)では、令和6年度から5年間で大規模改修等に美術館で計3億9300万円の費用を見込んでいるが、計画通り進められるかどうか現時点での考え方は
|
・計画に登載していることで交付税措置のある有利な起債を活用できることから、気仙沼市の単年度負担を軽減しつつ、平準化を図れると見込んでいる。貴重な文化的資料を今後も安全に管理しつつ有効活用していくうえで必要な修繕であり、計画通り進めることが前提だと考える
・公共施設等適正管理推進事業債は充当率90%で元利償還金の30~50%が交付税措置されることから、事業費の最大45%が交付税措置されると見込んでいる |
|
【最近の動き】
■ふるさと市町村計画広域活動計画策定住民協議会
・令和6年3月22日の住民協議会で次期計画の検討状況を報告
・組合の三浦事務局次長「市への移管が前提ではない。メリットとデメリットから検討する」
・山内館長「近いうちに最終方針がまとまる。最終方針が決まらないとこの先どうするか決められない」
・佐々木委員(気仙沼市観光協会)「フロー図で協議会の役割、住民の意見反映プロセス、決定者をハッキリさせ、責任を明確にして説明してほしい」
■気仙沼市に移管する方針を発表
・令和6年3月に正副管理者で協議した結果、気仙沼市の移管する方向で合意
・5月30日に移管準備担当者検討委員会を開催(6月に担当者部会)
・7月12日の正副管理者会議で令和8年4月に移管する方針をあらためて確認
・7月29日の組合議会全員協議会で経緯と今後のスケジュールを説明
■移管へ向けた議会での議論 ②
| 質問概要 | 答弁概要 | |
| 令和6年
11月22日 今川悟議員の一般質問 |
移管に向けた8つの検討項目の進捗状況は | ・移管後は教育委員会所管の教育機関に位置付ける
・組合教育委員会は廃止する ・美術館長と学芸員2人は組合から市へ身分移管し、事務職員と会計年度任用職員を合わせて現体制の12人を維持する方向で調整中 ・個別施設計画に記載している大規模改修事業の見直しを検討する ・令和9年度に予定している空調設備改修は維持管理費を含む総コスト抑制の可能性について検討を開始した ・移管後10年間の収支計画を作成する ・ふるさと市町村圏基金にある県補助金1億円は気仙沼市に引き継ぎ、運用益を美術館事業の財源にできるよう要望している ・収蔵庫内の保管スペース確保のため、移動可能なものを学校跡施設などへ移転保管することを検討 ・移管のための住民説明会は行わない想定 |
| 「支持される美術館像の追求」の検討方法は | ・約30年間積み重ねてきた美術館の実績を基礎としながら、移管後の美術館による新たな地域振興の可能性を模索する
・複合的な登録博物館施設の特徴を生かし、地域における美術・芸術文化活動の推進、歴史民俗資料の保存伝承活動の継続、東日本大震災を軸とする津波災害伝承、防災学習の推進について、近隣市町の関係機関との連携も視野に入れて、博物館施設としての社会的機能をより拡充していくことを目標とする |
|
| 円卓会議の今後は | ・活動趣旨は美術館の価値を地域住民に伝え、利用を促進するために多様な企画案を出し合い、潜在能力を見える化することである。移管に向けてはこの趣旨にのっとり、その機会を具体化することが一つの役割であり、移管後に想定される近隣市町の関係機関との連携も視野に入れ、新たな企画を円卓会議メンバーとともに検討する | |
| 2月10日
令和7年度予算案の質疑 |
・南三陸町から借りている資料もあり、手続きが必要になる
・広域文化圏として拡大していきたい |
|
■想定された選択肢
| 選択肢 | 効果と課題 | ||
| A | 現行のまま基金を積み増して計画を更新する | 気仙沼市の一時負担が大きい。手続きが煩雑で99%を負担する気仙沼市の意向が反映させにくい。計画期間は5年か10年かの検討が必要 |
人口減による財政緊縮により、いずれにしても美術館の運営費について抜本的な検討が必要 |
| B | 基金は廃止。運営費は毎年度の負担金として各市町が按分して拠出する。美術館の運営計画は策定する | 基金の管理が不要になり、予算も分かりやすくなる。市の財政負担は変わらず、移管しない理由について整理が必要。美術館の中期的な運営計画は基金の有無に関わらず必要である | |
| C | 気仙沼市へ移管 | 運営費のほとんどを負担する気仙沼市に移管することで、市の意向がストレートに反映される。南三陸町の関与方法について検討が必要。広域組合は消防専門になる。新たな広域連携について別途の仕組みを検討する必要がある | |
| D | 現施設の廃止 | 経費がかかるのは施設の大きさに起因するため、施設は廃止。文化振興に必要な美術館機能については気仙沼市が引継ぎ、他の公共施設等で規模を縮小して継続する | |