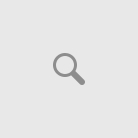気仙沼市議会の6月定例会が終わりましたので、その結果を報告します。報告第1弾は、中学校再編計画について議論した一般質問の成果です。
【中間報告の説明会の参加者少なく危機感】
4月に小中学校再編検討委員会がまとめた中間報告では、少子化を受けて中学校9校を4校に再編するとともに、再編を契機に小学校を含めた魅力化に取り組むという内容でした。9中学区単位で説明会が開催されましたが、保護者対象は計164人、住民対象は計89人でした。
 計画が策定されると後戻りは難しくなるので、説明会の参加を5月26日のブログで呼びかけましたが、期待していたよりも少ない出席人数でした。いろいろ話を聞いてみると、「もう決まったようなものだから仕方がない」「これだけ子どもが少なくなれば再編するしかない」と諦めて説明会に行かない人が多いことが分かりました。
計画が策定されると後戻りは難しくなるので、説明会の参加を5月26日のブログで呼びかけましたが、期待していたよりも少ない出席人数でした。いろいろ話を聞いてみると、「もう決まったようなものだから仕方がない」「これだけ子どもが少なくなれば再編するしかない」と諦めて説明会に行かない人が多いことが分かりました。
中間報告は学校の組み合わせだけでなく、統合の時期、魅力化の内容、統合した先の次の再編についても盛り込まれていますので、もっとたくさんの人に自分事として考えてほしかったです。
【スクールバスや教員配置の問題も】
一般質問では、説明会での教育委員会の姿勢、課題をはじめ、スクールバスの問題、代替案、指定校変更などについて取り上げました。
成果としては、最大14台も必要となるスクールバスをはじめとする通学手段の確保については、統合を最終決定する前に確認しておかなければならないことが浮き彫りにななったことをはじめ、市の予算で教員を配置することについて教育委員会も考えていること(低学年の少人数学級化用)などです。
個人的に深掘りできたなと思ったのは、「将来的には中学校は1~2校も視野に入れないといけない」との中間報告の表現について、しっかり決めていかないと約束していた気仙沼中学校の体育館新築も手を付けられないし、そのほかの施設改修や跡地活用も進めにくくなるという議論ができたことです。
【次の再編を決めないと施設整備が進めにくいのでは】
中学校9校を4校へ再編するのは、1学年1クラスの学校を増えていることを受け、早急な再編を進めることを目的にしたため、既存の校舎を活用することにしました。統合したも令和15年度にはまた1学年1クラスの学校が出てくるため、出生数を見ても将来的に1~2校にすることも視野に入れることになりました。その際には「学校の位置を含めた校舎の在り方も検討する必要がある」と中間報告で踏み込んでいます。
つまり、いまの考え方だと、4校に統合して10年もしないうちに、次の再編を進めることになる可能性が高いことになります。そのときは校舎の大規模改修とか新築も避けられないため、位置も含めた検討が必要になるということですので、そこがハッキリしないと施設整備計画も立てられないということになるのです。
気仙沼市は南北に長い地形なので、北部の拠点は気仙沼中学校に決めて、南部の拠点についても早急に議論すべきだと感じました(※その議論のために、作成した今川案をこのブログの最後に掲載しました)。
一般質問の質疑詳細は下記のとおりです(自分で書き起こしていますので公式な議事録ではありません)。今回は中学校再編の部分だけで、次回に残りりふるさと納税と公費で発生するポイントの取り扱いについて報告します。
今川悟の一般質問 令和7年6月25日
小中学校再編検討委員会の中間報告について
小中学校再編検討委員会の中間報告が公開され、保護者や地域住民向けに説明会が行われました。6月23日までパブリックコメントを実施し、今後は最終検討に進み、8月の答申、9月の再編計画決定が予定されています。市の将来に影響する重要な計画ですが、地域に諦めムードが漂う中、市民による議論が十分だとは感じられません。そこで、私が疑問に感じている次の5点について質問します。
質問① 中間報告の説明会では「決定事項の説明になっている」「意見を言えば見直されるのか」という参加者の意見に対し、教育委員会からの否定的な回答が気になりました。本来なら、意見を検討委員会に伝えることが事務局の役割だと思います。検討委員会と教育委員会の役割について、教育長の考えを伺います。
小山教育長 小中学校再編検討委員会の中間報告についてでありますが、検討委員会と教育委員会の役割については、まず、再編検討委員会は、教育長からの諮問に基づき、本市の少子化に伴う学校再編を含めた教育課題への対応と、学校の更なる魅力化に向けた答申をまとめるという大きな役割があり、この度、答申の中間報告がまとめられたところであります。
これらの協議を進めるにあたって、過去の義務教育環境整備計画における反省点を踏まえ、対話による市民の理解促進を重視し、小・中学生、保護者、地域住民等といった幅広い市民の皆様からの意見を積極的に聴取し、反映させております。
一方、説明会における教育委員会の役割は、再編検討委員会の事務局として、示された中間報告を市民の皆様に周知し、多様な意見を聴取する役割を担っております。また、これらの説明会で寄せられた意見や疑問点については、中間報告の内容や再編検討委員会での現時点での考え方に沿った内容で答弁させていただいております。これら説明会でいただいた意見は、すべて再編検討委員会に報告し、これらの意見を分析・検討して、最終的な答申を策定していただくこととしております。
質問② 中学校9校を4校に再編する案を実現するためには、単純計算で最大475人(受け入れ校以外の令和10年度生徒数の合計)のスクールバスを確保するという難題が生じます。これまでの統合によって閉校した学校から令和5年度は211人を対象にスクールバスを運行し、約8千万円を要しました。中間報告通りに統合した場合の必要な車両数とその確保策、費用と財源について検討状況を伺います。
小山教育長 スクールバスの車両数と確保策、費用と財源の検討状況についてでありますが、現在、中学校への通学支援については、スクールバス3校分4経路を4台で運行しております。再編に伴い必要となる通学手段の試算では単純に、スクールバスだけで換算すると、生徒数から見て14台程度が必要となりますが、運行形態、補助金の適用可否、既存公共交通機関の運用等、有効かつ機能的な経路の案を様々な角度から検討しているところであり、具体的な車両数や費用等については、財源も含め、今後詳細に算出してまいります。
質問③ 統合後のスクールバスや仮設校舎の費用を考えると、その費用で市町村費負担教職員任用制度を活用すれば、少人数学級や学校間連携に取り組んだり、外部人材やスポーツクラブ等への部活動移行を推進したりできると思います。子どもが減るから学校を減らすという対処的な考え方だけでなく、新しい発想でこれからの学校の在り方について考えていく姿勢も必要だと思いますので、教育委員会の考えを伺います。
小山教育長 学校再編に伴う諸費用の活用に関する教育委員会の考えについてでありますが、今回提示しました「中間報告」は、令和5年度までの出生数から予測される生徒数の急激な減少という喫緊の教育課題に対応し、本市の教育をさらに魅力化するための現時点での最善策として策定されたものと認識しております。
その内容は、再編検討委員会での審議の結果をまとめたものであり、小・中学生、保護者、地域住民、若者といった多様な方々からの意見聴取や、大学教授等の有識者の知見に加え、学校間距離、必要な教室数、災害ハザード等の客観的な観点や根拠に基づいております。
これらの点から、限られた時間と資源の中で、現状の教育課題を解決し、子どもたちのより良い教育環境を早期に実現するため、現時点において、この「中間報告」に示された内容が最良の選択であると判断しております。
質問④ 現在の出生数を考慮すると、中学校についてはさらに次の再編が避けられないことが明白です。4校への再編検討と合わせて、もっと踏み込んだ長期的な希望を持てるビジョンを示すことが必要だと思います。再編検討委員会の答申後の役割と合わせて、教育委員会の考えを伺います。
小山教育長 再編のビジョンと答申後の再編検討委員会の役割についてでありますが、中間報告に、中学校については将来的に「1~2校へのさらなる再編を視野に入れなければならない」と明記されていることを踏まえ、教育委員会としては、長期的なビジョンを持って、進めていく必要があるものと認識しております。また、8月に予定している答申後の再編検討委員会の活動については、現在の委員の任期が令和8年6月までになっておりますので、委員長と相談してまいります。
質問⑤ 中間報告の説明会に参加してみて、指定校変更の現状を市民に伝えるべきだと思いました。傾向を含めた現状、再編との関係性、制度の見直し、今後の情報公開について伺います。
小山教育長 指定校変更についてでありますが、令和7年5月1日現在、指定校変更を認めている児童生徒は、小学生が170人、中学生が83人であり、近年の指定校変更の申請理由といたしましては、教育的配慮によるもののほか、小学生においては通学の距離や安全面への配慮を理由とするものが多く見られております。
今後の再編との関係性については、通学距離が長くなることから、中学生においても安全な登下校の確保を理由として、通学先の相談の増加が想定されますが、本制度の趣旨に基づいた上で、個別の事情に対応できる体制を引き続き図ってまいります。
今後の情報公開については、指定校変更が許可基準に基づき、個別の事情を踏まえた上での判断となることから、本制度を促すような積極的な情報の公開ではなく、児童生徒や保護者の実情に合わせた個別の対応が適切であると考えております。
【再質問】
今川 最初に教育委員会と検討委員会の役割ですが、(昨日、一昨日の一般質問で)いろいろな議論がありまして、その中で私がそうだなと思ったのは、独立性と中立性という話でした。事務局として注意しないといけません。(説明会での)教育長の答弁とは異なっていて、傍聴していると教育委員会として現段階でここまで言わなくてもいいと感じました。見直しの可能性を問われて教育委員会として「難しい」と答えましたが、そうした意見を聞くための中間報告ですので、検討委員会で否定するなら分かるのですが、事務局として否定するのは違うと思ってこの質問をしています。
説明会が終わって、検討委員会が7月中に開かれると思いますが、今後の説明会も計画されていますから、そういう進め方も含めた諮問だと思いますので、委員会で議論していただきたいと思います。
スクールバスは最大14台必要ということですが、本当に必要となった場合に確保できますか。先日の質問でもありましたが、我々が議決するときに担保されていないと、希望があった分だけスクールバスを出すと今は言ったとしても、市内のバス会社で14台も出せるのかということは別問題で、小学生4キロ以上、中学生6キロ以上というルールを下回った場合、国から補助があるのかどうかも検討していると思いるのですか。
鈴木教育総務課長 台数の確保については、現在運行をお願いしている各業者に確認を行い、増加についての可能性について回答してもらっています。ある程度の台数確保は可能ということで見ている状況です。国の補助関係については、現在の補助基準が4キロ、6キロですので、見直しについて様々な要望を行っているところですが、具体的には生徒の分布、自宅からの距離なども見据えながらでないと実際のところは算定がしづらいところもあります。合わせてこちらも精度を高めていきたいと考えています。
今川 スクールバスについて確認しますが、現在の市の通学補助も中学校は6キロ以上となっていて、松岩や新月で保護者が運行するバスに補助していますが、気仙沼市は6キロを下回ってもスクールバスを運行すると説明していたと思うのですが、その通りでいいですか。
鈴木教育総務課長 これまでの説明会においては、「再編に伴い新たな負担が生じる部分につきましては、市の方で対応を」ということで説明してきています。この中で現在運行している公共交通機関の活用なども時間帯を含めて今後保護者の方にも提供しながら様々検討していきたいと考えています。
菅原市長 スクールバスの補助の制限についてはルールがありますが、ずっと宮城県市長会経由で国に要望を出している形になっています。しかし直談判をしていないので、早いうちに的を絞ってここをこう直してくれということで、直談判を展開していく必要があると思います。成果については今のところなんとも言えないところがありますが、全国のどこの町でもこの問題に正面からあたってしまっていることになりますし、地方創生2.0において、子どもたちの通学というか学習・学校環境の維持というのは大きな課題だと思いますので、一定程度の成果を得たいと思います。その時に距離の問題とか年数の問題とか、もっとハードルが高いのは一般人を乗せていいのかとか、そういうことまで考えないといけません。
しかしながら、一方で超過疎みたいなところがあったとすると、そういうことをしていかないとならないですが、もちろん民間のバスに対してフルの補助を子どもたちに対して出すというやり方もあるかもしれませんが、そういうことに今回は踏み込みたいと思っています。あとそのバスをどう活用していくか、昨日の議論の中で熊谷伸一議員さんとのやりとりでお示ししなかったのですが、実はワン・テン庁舎の利用のところでは学習スペースは書いてあるのですが、これって結構一般的にあります。あと、フリー学童のようなことも書いてありますので、帰宅のことと合わせてバスを有効活用することによって、効率を上げていくこともあると思います。
あと、教育委員会と話していないのですが、最大で見積もって1年目はやるようだかもしれないけれど、2年目からはそのバスのサイズが必要ですかということも当然あり得ます。なんかいつも半分しか乗らないとか、1/3しか乗らないのに、毎回50人乗りバスを動かすかというのもおかしいかもしれません。私はここはある意味決断を下して、経費と現状が見合ったような形で経費がどんどん無駄にかからないように運営していく必要があると思っています。
今川 いろいろハッキリしないところがよく分かりましたので、教育委員会が再編計画を策定するときには、そこをしっかり示していただきたいと思います。それで地域の説明会に行って、そのうえで議決ということで、しっかり懸念を整理することをお願いします。
お金がかかるのであれば、市の方で教員を増やせばいいのではというところは、前から否定的な話をもらっています。そこを踏み込んで、仮設校舎に5年で1億5000万円、年間3000万円もかけるのなら、小規模校のデメリットのうち教員を増員することで解決できることもあると思います。それが今の計画が最善策だからという話だと、中間報告の議論にもなりません。いろいろ検討した結果と選択肢を示して、制度の問題などを一緒に理解して前に進むべき思います。最善策だから排除していくという考えは違うと思います。もう一度、答弁お願いします。
小山教育長 中間報告は再編のみを手段としている内容ではなく、そのほかのいろいろな魅力化という言葉にはなっておりますけれど、ふれられているところです。例えば小学校は現状を基本というのも、徒歩で通学することの効果であるとか、地域密着で学習することの効果等も勘案されてのものだと理解していますし、あと今後の検討になるのですが、例えば指摘のありました教職員の市としての任用については、今年度で小学校の方が年次進行で35人学級がずっと続いてきたのですが、今年度で完成しました。小学校は全学年35人になりました。小学校の中でも特に下学年は就学時特有の特別な状況もありますので、例えばそういうところに少人数学級化ができないかということを市当局とも相談を開始しているところです。あと、これは以前から話していますが、中学校の教員による小学校専科担任の制度については、こちらも先行する形で今年度から取り組み始めたところです。再編だけを手段とするのではなくて、それと合わせた形でいろいろな工夫について取り組んだり、検討を始めている段階ですのでご理解願います。
今川 再編に伴って地域間連携とか教員側の負担が増えることも心配されます。再編するかしないかということではなくて、再編するにしても教育長がおっしゃる通り、現場の負担を減らす視点からも、市費負担の教員について検討をお願いします。ここで話したいのは、スクールバスが最大14台ということですが、例えば近いところは歩いていくとか、自転車で通学した場合に浮く費用を(教員増員などの)そういった費用に回すとかの話ができれば、皆さんから預かっている税金の使い方としては、何でもかんでも便利にするのがいいのか、不便さを享受する代わりにこっちへ投資をお願いしますという話ができると思います。
4点目の質問ですが、次の再編についてお願いがあります。市長も検討委員会の中で、松岩中に行くから将来的に松岩の校舎を使い続けるということではなく、例えば面瀬中を再利用するとか、旧気仙沼西高校を活用するとか、これから考えていかなければと話しました。ハッキリしておいた方がいいのは気仙沼中の体育館です。建設を考えているので、市の再編計画とするときには、将来1-2校になるときには、北部については気仙沼中を拠点として位置づけしないと、体育館の新築を進められないので、そこは頑張って頂きたいです。
南部に関しては、松岩中を一時利用したとしても、将来的に中心部に偏ってしまうので、その位置も含めて検討してほしいです。そういったことが、答申後の検討委員会の役割になると思います。検討委員会は条例によって、教育委員会からの諮問がないと調査できないという建付けになっているので、例えばこの諮問に対する答申が終わった後は、新しい諮問をしないと残り任期中の活動もできません。どういう風に考えているのか確認します。
清原学校再編推進室長 現在の小中学校の再編は令和5年度までの出生数に基づき、令和12年度までの小学校、令和18年度までの中学校の状況分析を踏まえた当面の課題解決ということです。この中間報告ですが、その答申の骨子となってその中には将来的には1-2校のさらなる再編が必要という認識は委員会の方でも共有されています。ただ、現段階ではその先の具体的な時期、それから学校配置ということはまだその中では触れられていないので、現在は申し上げられないところです。また、答申後の再編検討委員会の活動については、先ほどの答弁の繰り返しになりますが、やはりまだ決まっていませんので、委員長と相談しながら決めていきたいと考えています。
菅原市長 気仙沼中の体育館の問題は、今年(の予算)は調査的なものだから通していただけたと思っています。その次に進まないと棚ざらしみたくなるし、条南中の統合の時には気仙沼中の体育館は改修改築するという風に明言をしているというジレンマに陥っていると思います。教育委員会の答弁はジレンマに加えて自分で首を絞めた状態と思いますけど、ここはどこかのところで決めていかなくちゃならないと思います。
再編検討委員会については来年6月までだからということでお願いしている人もいます。気仙沼中の体育館のことはもしかすると結論を出せるかもしれないけれど、その先のことまで、半年間で何かできるというものではないと思うし、すべきでもないと思っています。気仙沼の南部についてということになると思いますけど、そのときはあらゆる可能性を排除できないだろうし、排除してはいけないと私も委員会の席で話したつもりです。いろいろ一長一短があって、市長部局としてはよくありがちなことですけれど、だったらどこに新しく建てるみたいな、いろいろなものを無駄にして新しく建てることが解決策でありますみたいなことについては、くみしないということだけは教育委員会に伝えていきたいと思っています。
今川 検討委員会がゼロベースで作り上げて、それを一緒に教育委員会が事務局で手伝った形になっていますけど、次のステップはおそらくある程度の案を出して諮問するという形で進めないと、理想と現実の部分でいろいろなギャップがあって、あとは教育だけでなく公共交通の話も関わってきます。そもそも土地が確保できるかという問題も出ますから、次のステップは早めに進んでいかないと令和6年度の出生数を見れば、1-2校という話が本当に現実的になっていますから、早めに議論を進めてほしいです。
あと気になるのは指定校変更の状況です。全体でみると、中学校は1136人のうち83人なので0.7%が指定校変更という形で部活動とかいろいろな理由があると思います。この現実を伝えることは、新月地区の説明会でも意見がありましたが、学区隣接エリアは指定校変更の対象になるルールがあるということ説明してほしかったです。毎回、情報公開しろというわけではなく、質問があったときに指定校変更で新月中学区から気仙沼中に何人通っていると説明できることが、理解につながると思います。説明会で実態を説明する考えはありませんか。
小野寺・学校教育課長 詳細の人数については、教育委員会としては把握していますが、教育長が答弁したように個別に配慮する案件でもあることから、学校再編で確かに学区が広がってということは想定されるところですが、制度の趣旨に基づいた上で個別の事情に対応できる体制を今後も引き続き図りたいと考えています。
今川 指定校変更制度が答弁にあったように個別の問題に配慮する運用だったら分かるのですが、実際は緩やかに運用されているので、ちゃんと皆さんに伝えた方がいいと思います。200人以上の児童生徒が利用している制度ですから、個別いいっていいのか、不登校の問題とも通じますが、全体の数字を出すのがいいのかどうかもあらためて検討していただきたいです。そういったことが市民の理解につながるからです。これから検討委員会が再開するので、その動きを注視します。きょうの質問はこれで終わります。
■下の資料は将来的に学校配置に関する私案です。通学距離や公共交通など気仙沼市全体を考えて作成しました